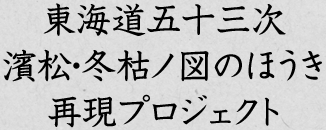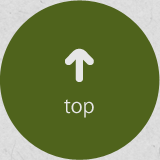第十七話 家康くんに献上 でもその前に。
[ ブログ ] 2015/12/04
歌川広重が東海道五十三次を描いたのは1833年、江戸時代の天保4年と言われています。わずか30数年後には明治維新を迎えることになるわけですが、江戸時代の、しかもここ『浜松のほうきを再現する』改め、『広重が浜松を描いた時に見たほうきを再現する』・・聞いただけでもなかなか面白そうです。
前回、とんでもない荒技の下、遂に箒が完成しました。いよいよ家康くんに献上です。でもその前に・・。
| K | 「テーマが変わってびっくりしましたけど、何とか箒を作れて良かったですね」 |
| Y | 「ほんと、ホッとした」 |
| K | 「でもせっかくなので、みんなで作ったほうき草を使って、浜松生まれの箒を作りませんか?」 |
| Y | 「・・・?」 |
| K | 「吾妻(あづま)箒です。アズマ工業が業界で初めて作った、それこそ浜松生まれの箒ですから」 |
戦後、全く新しい仕様の箒をアズマ工業で開発しました。今でいうカバー箒 です。

それまで座敷用の箒といえば、職人が編み上げる手編み箒だけでしたが、手編み箒の場合、ほうき草の茎部分を編み上げる仕様のため、その茎の分だけ重くなる欠点がありました。特に家中をお掃除する場合、軽さが求められますので、この欠点は少々痛いところがあります。
また、手編み箒の場合、掃き心地に直接影響のある穂だけでなく、編み込みのために茎部分も必要となり、より厳選した穂のみを使用しなければならず、その分コストに跳ね返ってしまいます。
それらを改善すべく、重さの原因である箒草の茎部分を切り落とし、穂先だけを均一に揃えたものを結束する手法がカバー箒です。穂先だけを使いますので、茎の良し悪しを考慮しなくてもよく、収穫したほうき草をより有効活用できるというメリットもありました。
アズマ工業は、このカバー箒に「吾妻箒(あづまほうき)」というブランド名をつけ全国に向けて販売し、掃除機に押され縮小していた座敷箒の市場を復活させ、座敷箒メーカーとしての礎を築きました。現在の社名「アズマ工業」も、実はこの「吾妻」に由来しています。
| K | 「吾妻箒、つまりカバー箒はアズマが初めて考案した箒なんですよね」 |
| Y | 「実用新案も取得していたから、そうだね」 |
| K | 「ということは、浜松生まれの箒ということですよね」 |
| Y | 「・・確かに」 |
| K | 「せっかく家康君に会えるんだから、吾妻箒を復活させて献上してもいいんじゃないんですか。家康君をモチーフにしたカバー箒を作っても面白いと思いますし、未来に向けて、全く奇抜なカバー箒でも面白いと思います」 |
| Y | 「・・確かに・・・」 |
| K | 「じゃ、決定!」 |
こうして、『広重が浜松を描いた時に見たほうき』と『浜松生まれの吾妻箒』を献上することになりました。せっかくなので、今までほうき草を一緒に作っていただいたJA様とカバー箒を作ることに。
| K | 「私の提案が採用されるなんて、ものすごく感動しています!」 |
| Y | 「なんかここにきて、さらに元気になったね。・・・・なんかすっごく嫌な予感がするんだけど・・」 |
| K | 「とか、何とか言っちゃって。実は期待しているんじゃないんですか? 私の突撃レポートを」 |
| Y | 「いや。まった・・」 |
| K | 「そんな遠慮しなくても大丈夫です。最後はやっぱり元気よく締めなきゃだめですからね」 |
| Y | 「・・・・(小声で)首を絞めなければいいんだけど・・」 |
| K | 「えっ?」 |
| Y | 「いやいや頑張って。そうだね。元気よく絞めなきゃね、いや、締めなきゃね」 |
| K | 「任せてください。よーし、やったるかーーー」 |
というわけでここからはKさんにバトンタッチ。
・・・・・・・・・・・・
しっかりバトンを受け取りました!ここからはKが進めさせて頂きます!
タイトル:JA様とコラボで箒作り!
(またしても懲りずに勝手にタイトルを変えてしまいました)
さて、今までほうき草作りでお世話になったJAとぴあ浜松青壮年部の皆様を招待してのアズマ工業での箒作り体験!いよいよ明日に迫ってきました。もう最高にテンションが上がっています。
大勢の方に支えられ育てられたほうき草が念願の箒になると思うと、いてもたってもいられません。ブルーシートを敷き、ほうき草を並べ、準備が一通り整ったところで一人「うん、うん」。我ながら最高の仕上がりです(準備だけですが)!
| Hさん | 「Kさん、はりきって準備をしているところ悪いんだけど、明日の朝のラジオ体操はどこでやるの・・・?」 |
すっかり忘れていました。アズマ工業では、今回箒作りをする会場で、毎朝ラジオ体操を行っています。
| K | 「・・・中庭でどうですか?」 |
| Hさん | 「雨が降ったら?」 |
| K | 「・・・て、てるてる坊主を作ります」 |
さっそく空回りをしてしまいましたが、箒作り当日は晴れ!お天道様も応援しているようです。ラジオ体操も中庭で行ってもらいました(協力ありがとうございました!)。
11月4日午後1時、総勢約20名の皆さんでさっそく箒作り開始!
今回はアズマ工業製造部のTさん、Iさんから箒作りを教えてもらいます。
まず、約20本のほうき草を手に取り針金で結束します。この針金を撒く作業、お掃除の最中に穂が抜けないようにきつく巻かなければいけません。パレットを使いながら針金をギュウギュウに巻き付けます。こんな感じです。

| K | 「手編み箒と比べてそれほど技術もいらないし、皆さんと楽しくできると思って提案したんですが、正直こんなに力がいる作業だとは思っていませんでした。手が震えています」 |
| I |
(遠州弁丸出しのIさん、決して怒っているわけではありませんのであしからず。) 「これだけで根をあげちゃダメじゃん 。これからが本番だに 」 |
| I | 「それにKさん、ちゃんとほうき草を揃えないとダメだに 。均一に穂の根元を揃えないと掃きムラがでるで」 |
力だけじゃなくって、コツも必要なようです(当たり前ですが・・)。
一通り針金で巻く作業を終え、次は茎の余分な部分を切り落とす作業です。
もはやしゃべる人はほとんどいません。ノコギリと木づち、ほうき草のガサガサいう音だけが聞こえ、みな集中して作業を進めます。

女性も大活躍。見事なノコギリさばきです!

このような形になりました。これを木づちで叩き、樹脂カバーに収まるように平たくします。
金づちを使用すると、ほうき草を傷めてしまうため、ここでは木づちを使用します。

この束を数個並べ、竹串を刺して柄に固定します。
きつく固定したほうき草に串を刺すのは、これまた一苦労です。

柄を挟んでそれぞれ両側にほうき草を差し込み、余分な竹串をノコギリで切り落とします(本来はナタみたいなもので切り落としますが、さすがに初心者には危ないのでノコギリにしました)。
ここに樹脂カバーをかぶせ、ようやく箒に見えてきました!

最後にもう一仕事!樹脂カバーとほうき草を完全に固定するため、タッカー針を打ち込みます。
機械に頼らないモノ作り、ということで、今回は金づちを使い固定します。

| 青 | 「箒作りってこんなに大変だったんですね。ホームセンターで何百円で売られていることが信じられない」 |
| K | 「私も正直、なめていました。こんなに箒作りが大変だなんて・・・」 |
少々不格好な箒もできましたが、この日、約16本が形になりました!


家康くんへ献上する箒はイラストを貼った特別仕様です。
後日、製造部で仕上げをし、完成です!

お待たせいたしました!次回、いよいよ家康くんに献上です。